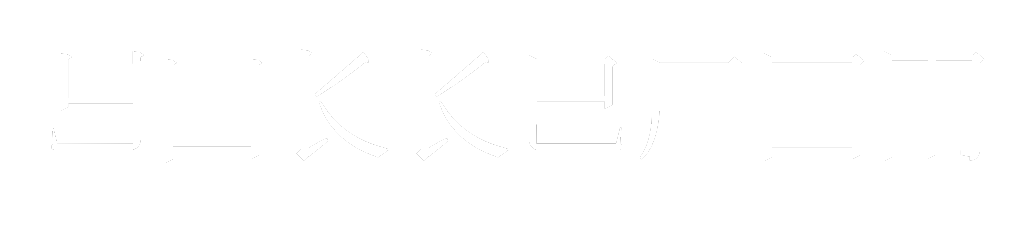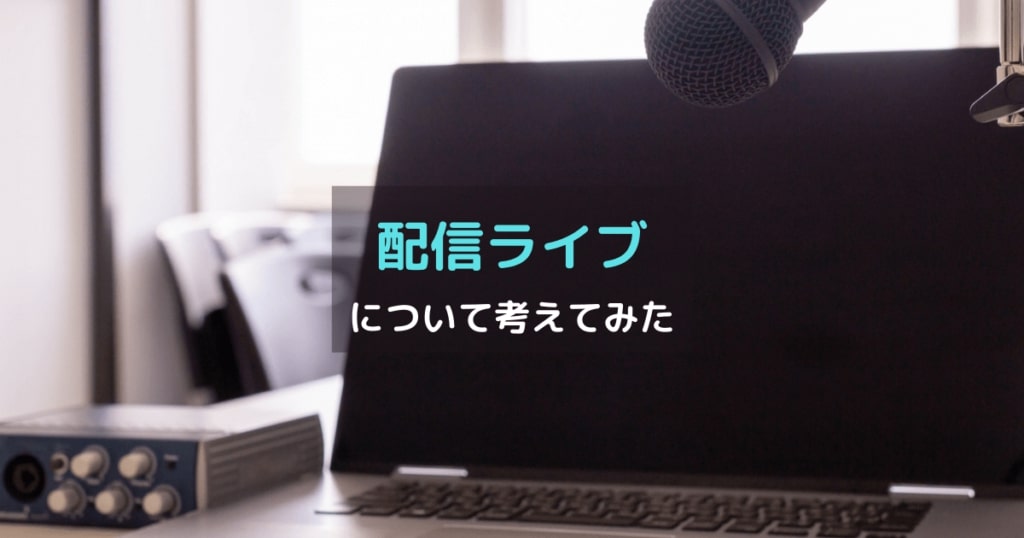今日は最近目にする機会が多くなった、”配信ライブ”について考えてみようと思います。
先日、yukkeromのVJを担当してくれているRASTERさんのワンマンライブを視聴。
僕はこの配信をリアルタイムで見ていて、”今後のライブ配信に対するアンサー”を考えました。
今回はRASTERの配信ワンマンライブと同じくらい衝撃的な配信ライブだった【Omodakaのワンマンライブ】の2本を取り上げて、配信ライブについて考えてみようと思います。
Youtubeなどの無料配信ライブのメリット
配信ライブのあり方を考えるために、まず配信ライブのメリット・デメリットを整理します。
まず、RASTERとOmodakaの配信ライブを振り返って、どんなメリットがあるかを考えてみました。
お客さんは場所を選ばずにライブに参加できる

配信ライブの一番のメリットは、
ライブ会場に行けなくても、パソコンやスマホがあればライブに参加することができる。
ということだと思います。
実際、僕も2020年は、コロナウイルス感染症が流行している中で、
- 社会福祉施設で働く職員として
- 一児の父として
ということを考え、外に出ることを控えていました。
「子供が生まれてから、あの人全然ライブハウスで見なくなったな…。」
こんなことを以前感じたことがあります。
家族が増えることで夜の行動に制限がつくのは子供ができるとよくわかるようになりました。
(僕は嫁の協力のおかげでULTIMALAのスタジオやyukkeromの活動ができています。ありがとうユッケヨメ。)
色々な理由でライブハウスに行けない人も、配信ライブを利用すればライブに参加できるということは、大きなメリットといえるでしょう。
アーカイブがあれば何度でもライブを見ることができる
配信ライブはアーカイブしてあれば、いつでもライブを見返すことができます。
その時のチャット欄を残しておくことも可能なので、当時のことを思い出すことができますね。
実際にライブに参加していても、
「仕事の重要な電話でどうしても一回会場を出なければいけない…。」
という時にも、アーカイブがあれば後から家に帰ってライブ映像を確認することができます。
現実では難しい演出が可能
現実では難しい演出も、配信ライブであれば可能になります。
楽器を使った配信ライブならライブでは見ることのできない角度から演奏映像を見せることが可能ですし、それ以外にも様々な演出が可能。
壮大な配信ライブの可能性を見せてくれたのが、Omodakaの配信ライブでした。
Omodakaの世界観に合わせた映像がリアルタイムで編集されているので、お時間のある人は是非見てみてください。
最初にお話したRASTERの配信ワンマンライブも、
- バラエティー番組風の演出
- 曲に合わせた映像とライブ映像をミックス
- 普段と違うバージョン演奏(バンドバージョン)
等、見ていて楽しいエンターテイメントとして完成された配信ライブでした。
Omodaka、RASTERともに、配信ライブだからこそ映える演出をしたことで、”エンターテイメント”として鑑賞できる配信ライブになっていたではないかと思います。
Youtube等の無料配信ライブのデメリット
次に普通のライブに対して、配信ライブでは充当するのが厳しい点を考えていきます。
ライブハウスの様な環境で音楽を聴けない人が多い
爆音で音楽を聴くことができることは、ライブハウスの大きな魅力の一つだと思います。
ですが、配信ライブでは、お客さんが様々な環境でライブの音を聴くため、ライブハウスの雰囲気を感じることが難しいです。
「爆音を身体で感じたい!」
というリスナーには配信ライブは不向きかもしれません。
また、配信ライブではライブハウスと違い、”ライブに集中できる環境”が用意できないことが多いです。
- YouTubeであれば横に出てくる関連動画
- 配信を見ているときに鳴るLINEの通知音
等、様々な要因で、仕掛けがない配信ライブはライブハウスでのライブに比べて、最初から最後まで視聴してもらうことが難しいと考えられます。
限定性が薄い
ライブハウスでのライブの魅力に”ライブは生き物である”ということがあります。
ライブは何が起こるかわからず、その場にいた人達だけがそれを見ることができるという”限定性”はライブの大きな魅力。
配信ライブではメリットの部分で挙げた”アーカイブ”としてライブの映像が残りますので、この”限定性”が薄くなってしまいます。
“限定性”が薄れることで、”別に今じゃなくても、そのうち見ればいいや”というものになってしまい、結果的にライブそのものの質を下げてしまう危険性があるのではないでしょうか?
アーティストと対面していないので熱量を感じにくい
ライブ配信に参加しても実際に対面していないので、視聴者が演者の熱量を感じるのが難しく感じます。
ちょっと話がそれるかもしれませんが、2020年中は仕事でZoomのいろいろな研修に参加しました。
研修で、Zoom内でグループワークをしたとき、全く意見が出なかったことがあり、他の参加者に話を聞くと、
「実際に顔を合わせてないから、場の空気がわからなくて、なんだか意見が言いにくいです…。」
とのこと。
確かに、オンラインで集まる時には、対面での集いよりも”その場の空気”を感じることが難しく感じます。
ライブに関しても同じで、ライブハウスの熱量を自宅で感じるのはなかなか難しいのではないでしょうか。
配信する側もお客さんの雰囲気を感じにくいので、どのようにお客さんと演者がコミュニケーションをとっていくかも配信ライブを行う上で考えていく必要があると考えられます。
今後のYoutubeなどの無料配信ライブのあり方
今まで挙げたメリットやデメリットから、僕が考える配信ライブのあり方は次の通りです。
普段と違うリスナーの獲得方法として
“ライブハウスに行く”と様々な魅力を感じることができますが、
- 一人では行きにくい
- 気になるアーティストのライブは月に1回程度で予定が合わない
- 音楽の趣味があう友達がいないので誰かと行くのが難しい
等の理由で、最初の一歩を踏み出しにくい文化であることは否めません。
そういった時に、配信ライブなら、今までライブハウスに行ったことが無い人も自宅で気軽に配信ライブに参加できるので、アーティスト側からすると、新たなリスナーの獲得の機会を得たことになります。
もしコロナウイルス感染症が落ち着いて対面でのライブが復活したとしても、配信ライブは新規リスナー確保や音楽の新たな楽しみ方の一つとして継続していって欲しいというのが僕の思いです。
お客さんに楽しんでもらうため、配信ならではの工夫をする
配信ライブを一つの文化として継続していくには、“ライブハウスでのライブが難しいから行うもの”という物から”配信でしか見られないエンターテイメント性のあるライブ”になる必要があると考えています。
爆音、轟音でない状態で視覚的に訴えかけるものなどがなければ、配信ライブはストリーミングの下位互換となりかねません。
私、yukkeromも2020年の初頭に数本の配信ライブに出演しました。
これはイタリアの配信ライブに出演したときの映像です。
以前ライブの後に、
「チップチューンの人はライブの時に何をしているのかわからない…それが見られたらもっと面白いのに!」
という意見をもらったことがあったので、配信のメリットを活かして、手元の画像を合成した映像を配信しました。
いろいろな試みをトライ&エラーしていって、自分のアーティストとしてのアイデンティティーに合った配信ライブを行うことが大切ではないかと思います。
今回序盤でお話したRASTERとOmodakaの配信ライブでは、その自分のアーティストとしての世界観的なものが音源、映像、ライブの構成等から伝わってきました。
自分もこれらの配信を参考にして新しい試みを考えてみようと思います。

可能性を秘めた配信ライブ、有効に活用していきたい!
デメリットや難しさもありますが、様々なメリットや可能性がある配信ライブ。
- メリット①→リスナーがどこからでも参加できる
- メリット②→映像だけでなく、チャット欄も見返すことができる
- メリット③→現実ではできない演出が可能になる
という3つのメリットを活かしつつ、
- デメリット①→爆音で音楽を聴ける環境でないところで視聴されることがある
- デメリット②→”今いる人しか経験できない”という限定性は薄い
- デメリット③→対面していないので、熱意が伝わりにくい
という3つのデメリットをバンドやアーティストの世界観に合わせて解消することが大切だと思います。
具体的に”これが正解!”とか”こうすればうまくいく!”といった答えは、それぞれのアーティストによって違います。
僕も自分のスタイルにあった配信ライブを検討してみようと思います。
今後、面白い配信ライブのアーカイブを見つけたら、まとめて紹介してみようと思うので、記事ができたときにはチェックしてくださいね!
それでは!