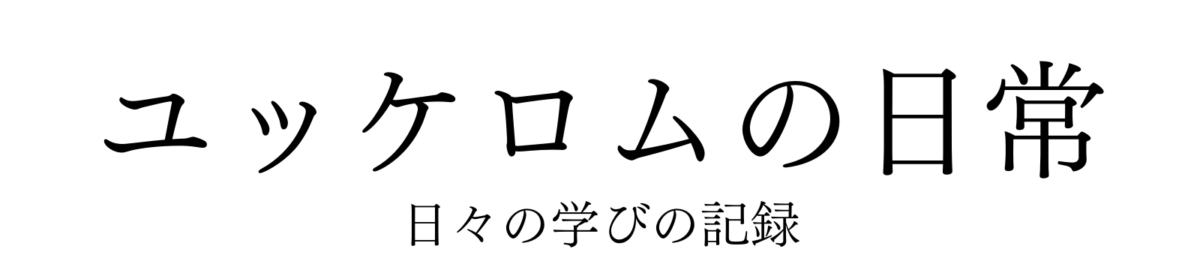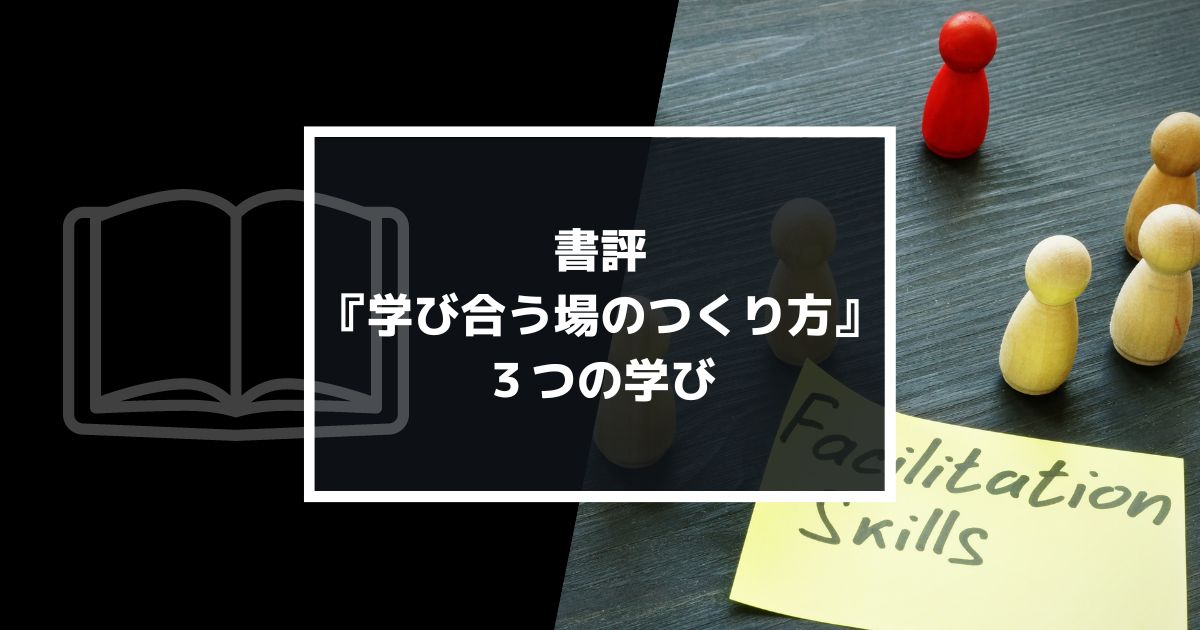様々な社会教育系の研修でたびたび紹介される、『学び合う場のつくり方』。
以前購入して手元にはあったんですが、中々読めていませんでした。
昨日読了したんですが、なんでもっと早く読まなかったのかと後悔するくらいいい本です。
色々な人に読んでもらいたいけど、常に手元に置いて仕事などで使いたいので貸す事が出来ないくらい名著だと感じました。笑
今回は自分が重要だと思ったポイントを3つまとめたので、もしよければ最後までお付き合いください!
『学び合う場の作り方』はどんな本なのか?
まず『学び合う場のつくり方』についての基本情報は下記の通り。
| 著者 | 中野民夫 |
| 価格 | 2,200円(税込) |
| 発行日 | 2017年6月15日 |
| 出版社 | 岩波書店 |
中野民夫さんは博報堂勤務後、早期退職から同志社大学教授、東京工業大学の教授という経歴の持ち主。
ワークショップやファシリテーションのプロということで、『学び合う場のつくり方』ではファシリテーションの技法について自身の経験を踏まえて分かりやすく解説されています。
ページ数は198ページですが、引用などを詳しく書いている関係で実際のページ数はそんなに多くない感じがしました。
ビジネス書とかと比べると文字が小さく、最初はちょっととっつきにくかったですが読んでみるとすんなり読むことができる一冊です。
そんな『学び合う場のつくり方』で僕が重要だと思った3つのポイントを紹介します。
『学び合う場の作り方』、3つの学び

学び続ける過程こそ大事
『学び合う場のつくり方』、冒頭から度肝を抜かれたのが、
行動に意味ある影響を与える学習とは、自己発見的、自己獲得的な学習だけであると感じるようになってきた。
『学び合う場の作り方』序文
という一言。
教える側がこちらから”教える”というよりも”学びあう”という考えを持つことの重要性を学ぶことができました。
年齢が高くなるにつれて、どうしても
どうすれば伝わるか…?
ということを考えがちなんですが、それよりも
どうすれば本人が気づけるのか…?
ということを忘れずに人と関わるようにしていきたいですね。
ファシリテーター、5つのスキル
『学び合う場のつくり方』ではファシリテーターに必要なスキルを下記の5つにまとめています。
- 場作り
- グループサイズ
- 問い
- 見える化
- プログラムデザイン
上記5つのスキルについて詳細に書いてあり、実際に事業やプログラムを組むときにかなり役立つことがびっしり。
場づくり
まず場づくりに関しては”物理的な場”と”心理的な場”についてそれぞれ状況に応じて設営が必要とのことなんですが、一番学びになったのがオリエンテーションにおけるOARRという考え方。
OARRとは、
- Outcome(目標やゴール)
- Agenda(スケジュールややること)
- Role(役割)
- Rule(ルールや決まり)
というものでOARRに沿うと良いオリエンテーションとなってきます。
オリエンテーション以外でミーティングや会議などでも使えるものなので、積極的に使って身につけたい所です。
グループサイズ
2人組、3人組などのグループサイズ、どれが一番いいということではなくそれぞれ一長一短。
グループワークを仕切る時とか、結構迷ったりするんですよね…。
何人組が有効なのかを丁寧に説明してくれているので、『学び合う場のつくり方』を都度見返して適切な場の設定をしていきたいです。
問い
どんな問いがいいのか?『学び合う場の作り方』では下記の様な問いが好ましいとされています。
- 共通で触発的な問い
- 身近で具体的な問い
- ポジティブで楽しい問い
- 自分の体験から
- 裁かれる恐れのない問い
改めて見てみるとなるほどとなりますね。
これも実践を重ねて状況に併せた問いを考えたり、自然に上記のような問いができるようになろうと思います。
見える化
話したことを記録して可視化すると整理されやすいということから、見える化は大切であるとのこと。
高齢者向けの事業を中心にやってきた為か、ふせんを使ったワークや何かを記録しながら行う事業をあまり企画してこなかったので、意識して取り入れていかないと中々自分の物になっていかなそうだなーと反省しました。
あと、勝手に要約せずに、その人が話した言葉を使うながら書くということも自分があまりできていないポイントだなーと反省。
相手のあるがままを受け入れて相手が話している間は全てを聞く、意外と難しいんですよね…。
意識しないと途中で自分の頭で考え始めてしまうので、いったん相手の言うことを聞くのをしっかり意識していこうと思います。
プログラムデザイン
本書に記載されているプログラムデザイン曼荼羅を活用して組み立てると良いとなっています。
目標に合わせて起承転結を持たせたプログラムデザインをできるツールとしてとても面白いものだと感じました。
これに関しては騙されたと思って一度読んでみて欲しいです。
人に関わるものとして大切なことは何だろう
最終章で書かれている”人に関わるものとして大切なことはなんだろう?”について書かれている一文がとても印象的だったので引用します。
「教えよう」「変えよう」と頑張るよりも、自分が他でもない自分自身になりきること。そして一緒に底にいる相手が相手自身になりきることをただ許し、楽しむこと。
『学び合う場のつくり方』
教育、ファシリテーターだけでなく、対人援助に関わる人にも言えることですね。
ただ相手のそばにいること。
時間をきちんと取り、余裕を持って万全の体制で相手と接することの重要性を再認識することができました。
常に手元に置いておきたい!ファシリテーター必携です!
『学び合う場のつくり方』、予想以上に勉強になるし困った時にすぐ読み返したい1冊です。
人を支援することについてのヒントも多い一冊だと思ったので、福祉職(特に社協職員)におススメですね。
ファシリテーション、慣れてくると自己流になって本書に書いてあるポイントがないがしろになったりしがち。
事業の度に確認して、ポイントを押さえてよりよい学び合うを作れるようにしていきたい所です。
冒頭にも書いた通り、使いたい時に手元に置いておきたくなる1冊なので購入がおススメ。笑
1冊2,000円以上と普通の本に比べると少し高価ですが、その価値はある一冊じゃないかなと思います。
それでは今日はこの辺で。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
※僕の読書履歴、こっそり記録してるので興味があるという奇特な方はこちらもご覧ください。