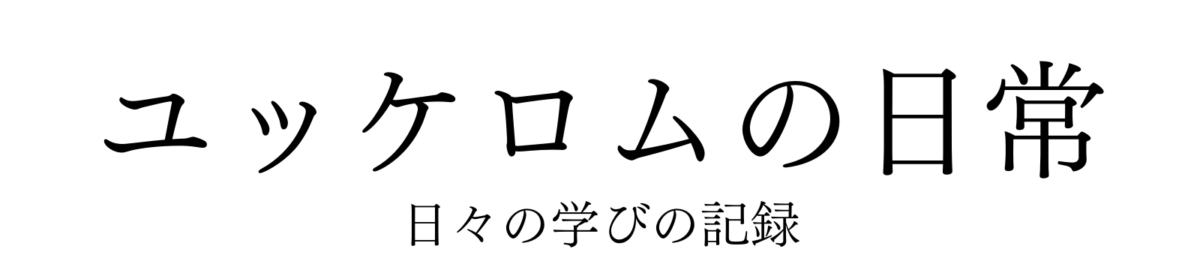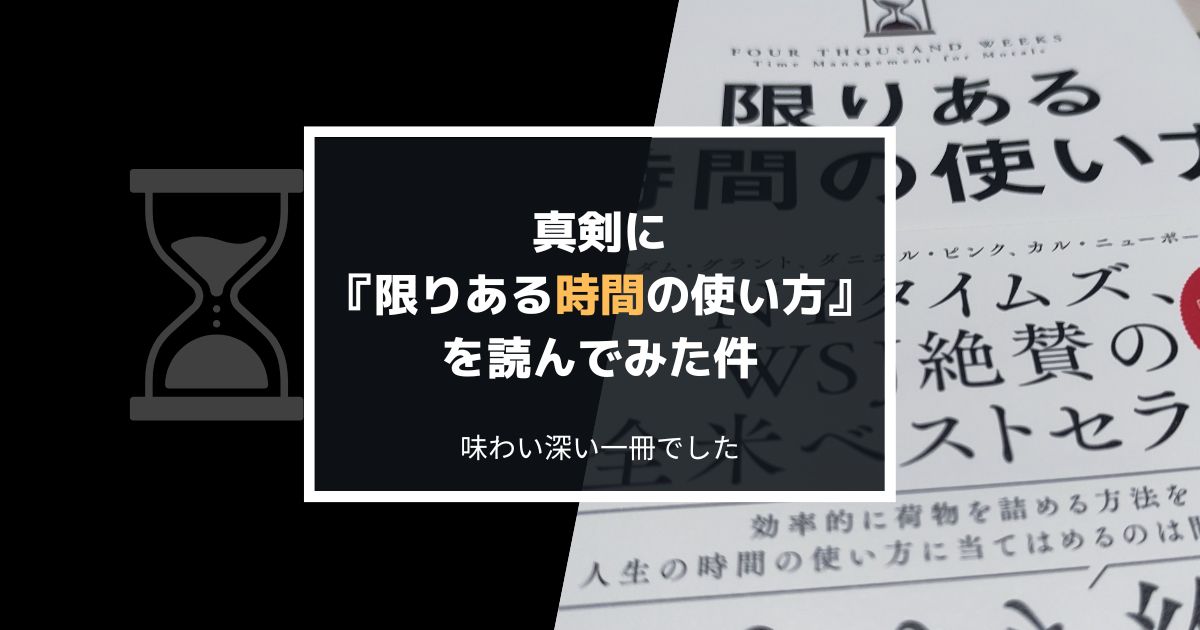いつも本を買うTSUTAYAに行って本を買いに行ったある日。
“あのひろゆきも絶賛!”という謳い文句が気になって購入したのが、今回読んだ『限りある時間の使い方』でした。
タイムマネジメントとか、ライフハック大好きおじさんだったので、
「今回はどんな有益な情報が得られるのだろう…!」
と思って読み進めてたんですが、タイムマネジメント、ライフハックという幅を超えて、人生について考えさせられる予想以上に価値のある1冊でした。
“効率化を図って自分で自由に使えることが幸せへの一歩!”
と思っていた自分には衝撃的な1冊でしたね。
特に重要だと思ったポイントをまとめておいたので、もしよければ最後までお付き合いください。
『限りある時間の使い方』はどんな本なのか?
まず『限りある時間の使い方』についての基本情報がこちら。
| 著者 | オリバー・バークマン 高橋 璃子(翻訳) |
| 価格 | 1,870円(税込み) |
| 発行日 | 2022年6月22日 |
| 出版社 | かんき出版 |
Amazonの”仕事術・整理法”カテゴリ1位を獲得している、『限りある時間の使い方』。
本のタイトル的にタイムマネジメントやライフハック系の本っぽく見えるんですが、時間の使い方に関する本質的な部分から考える一冊となっています。
タイムマネジメントやライフハックは”効率的に時間を使って自由な時間を多くする”ために行いますが、それが本当に幸せなのか?ということを考えさせられました。
筆者がもともとタイムマネジメントやライフハックにハマっていた体験談を交えながら説明してくれるおかげで、本の内容が腑に落ちる感じがします。
『限りある時間の使い方』、3つの学び
タイムマネジメントやライフハックに見切りをつける
“時間を思い通りにコントロールしようとすればするほど、時間のコントロールが効かなくなる。”
自己啓発やタイムマネジメント系の本を読んでは、
『自分がだらしないから中々習慣にならないんだな…今回こそ長続きさせよう…!』
をかれこれ10年以上繰り返していた僕にとって、このとこについて書かれていた本書はとても新鮮でした。
今という時間を未来のために使うということは、楽しみが先延ばしになっているということで、時間を支配しようとすればするほど時間に支配される。
これが本書一番の気付きかもしれません。
改めて考えてみると、マインドフルネスをしている時にも、
『これが終わればすっきりした頭で次の行動に取り組める。』
という考えを持ってしまったりしていた気がします。
本来であればマインドフルネスという行為そのものを楽しむ、常に自分に与えられた時間を楽しむことが大切ということを本書で学びました。
“何のために生きているのか?”ということよりも”今をありのまま楽しむ”ということを受け入れるという視点は、人生を考える上で大事にしたい考え方です。
また、”時間があるという前提を捨てる”ことも忘れないようにしたいですね。
人生は有限で、必然的に2度とない経験であるということを考えると、どんな時間も楽しめるのではないかと思えるようになりました。
あとこの本で触れられている”自分の有限性を受け入れる”ということは、デスカフェと通じるものがあるなーと感じます。
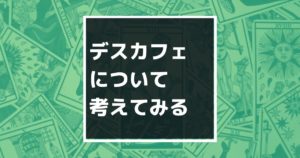
“何もかもできないこと”を受け入れる
“人生を生き切った”と感じることは実質不可能。
体験が無限に対して人生は有限であるということを受け入れておくことが重要ということも大きな気付きでした。
だからこそ、人生において”やらないことを選ぶ”ということはとても大事なんですね。
自分が本当にやらなくていいことは何か?
時間があるという前提を捨てて、考えることで日々の過ごし方が変わってきます。
あと、“効率的にやれば忙しさから逃げられるという希望を捨てる”ということも忘れないようにしたいポイント。
効率化しても、やることは終わるどころか増える一方というのは、仕事をしていてわかる気がします。
手を付けない不快感を受け入れる、耐えるということの重要さを忘れないようにしたいです。
本書で紹介されていた、忍耐のポイント(下記参照)を意識して自分も耐え忍んで生きていこうと思います。
- “すべての問題を解決できる”という達成不可能な目標をあきらめる
- 何事も毎日コツコツと進め、やりすぎない
- コピーからオリジナルが産まれる
完成を空想にしておくのか?
“先延ばしは、完成を空想にしておける。”
仕事を先延ばしにする理由として非常に腑に落ちるものでした。
やりたかった仕事、なぜ進みが悪くなるのかもこれで説明が付きます。
完璧な仕事なんて誰にもできないから、肩の力を抜いて、まず始めてみるということ。
これを意識すれば、いくらか楽に仕事に手を付けられそうな気がします。
その他、忘れないようにしたいこと
その他、本書で忘れないようにしたいなーと思ったポイントは下記の通り。
- 非目標性の活動(趣味)は活動そのものを楽しめる
- 選択は貴重な時間の過ごし方を自分自身で考え、選び取った結果
- 不便なことの手ごたえこそ人間関係を深め、心身の健康やコミュニティの健全さを保つのでは?
- 他の人がいるから、物事には価値がある
- 個人主義的な自由時間の増加は、果たして本当に幸せなのか?
- 不安をコントロールしようとする努力が不安を生む・人間は常に不安を持つもの
全体的に、”言われなくても知ってるよ”と思いそうだけど、改めて言語化するとそうだなーと思いました。
③の不便なことこそ~というもの、スマートフォンの普及で電子マネー決済などかなり利便性が高くなったことで人とのかかわりが少なくなったということはわかりがあります。
レジもスマートになった分、昔ほど店員さんとの繋がりが無くなった気がしますね。
昔、深夜コンビニのバイトをしていた時に常連さんのたばこの銘柄を覚えていたのがきっかけでレジを打って会計している時に話をして仲良くなり、退職の日に差し入れを持ってきてくれたことが頭をよぎりました。
便利な世の中になればなるほど、人と繋がるには意図的に話す必要が出てくる。
いいような悪いような、考えさせられました。
あと、”個人主義的な自由時間の増加は、果たして本当に幸せなのか?”というのはかなり心に刺さりましたね。
FIREしたら、本当に自分は幸せなのか?
そんなことを考えながら本書を読んでたら、読了まですごい時間かかりました。笑
人生について考えさせられる1冊でした!
タイムマネジメントの本だと思って買った、「限りある時間の使い方」。
予想以上に人生について深く考えさせられる1冊でした。
各所で様々な哲学者の言葉が引用されていたんですが、その言葉が的確だったのも筆者の博識が伺えましたね。
古くから残る哲学者の思想には様々なヒントがあることを学んだので、近々古典的な哲学書も読んでみたいなーと思いました。
考えながら読んだせいなのか、師走に入る忙しいタイミングだったからなのかはわかりませんが、今年読んだ本の中で一番読むのに時間がかかった1冊。
非常に味わい深い本だったので、気になる人はぜひ読んでみて下さい。
それでは今日はこの辺で。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!